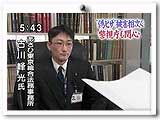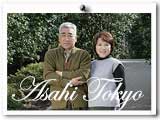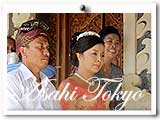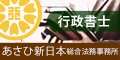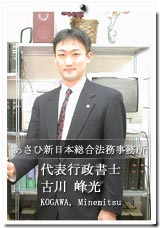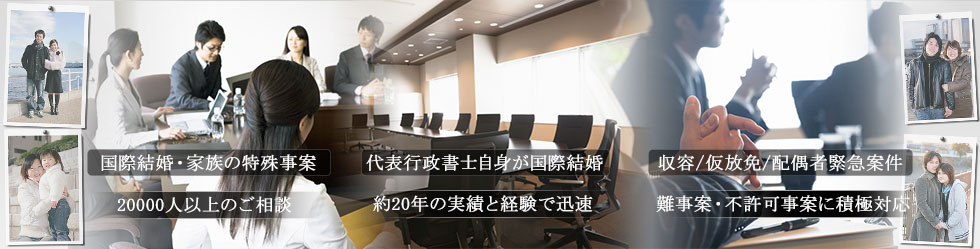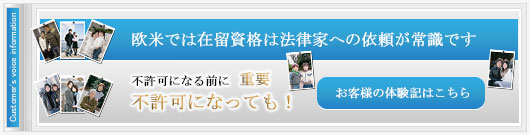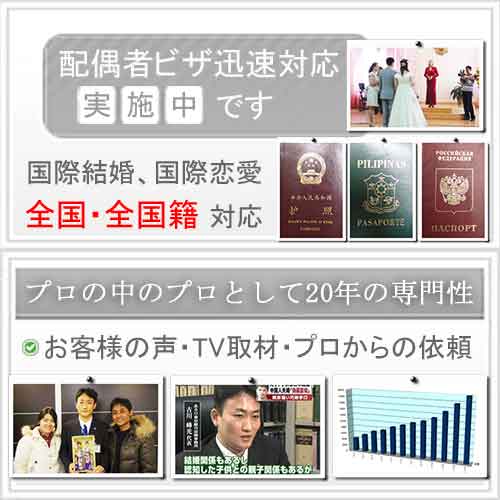ここでは配偶者ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士が、経験と知識をアレンジして、Q&A形式でお答えいたします。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの配偶者ビザの一口アドバイス‡
配偶者ビザの実務は基本書類と応用書類で構成されます。この配偶者ビザのポイントは、国政結婚手続きにおいても、配偶者ビザの在留資格の申請においても、結婚相手の国によって必要になる書類は異なってくることです。一般に、偽装婚の多い国になるほど、書類や手間は増える傾向です。また、日本人配偶者の場合、在留申請の受付には、最低限、婚姻届けの受理証明書が必要ですが、国際結婚の場合、日本人同士のように、婚姻届け「だけ」を区市町村の役所へ持っていっても、通例は受理されません。一般には外国人側の「婚姻要件具備証明書」等が求められ、これが出ない国だと、法務局への受理照会扱いになり、時間がかかる場合があります。「婚姻要件具備証明書」の内容と要否は、国籍と、戸籍の審査をする市区町村職員によって異なります。また、先に相手の外国での婚姻を先行させる方法もあります。国に拠りますが、日本人側の婚姻要件具備証明書につき、法務局-外務省-領事館の3点認証などをする場合もあります。そして、これらがなぜ配偶者ビザに関係あるのかと申しますと、配偶者ビザの立証資料の組み立てには渉外戸籍の知識が必要になるためです。
- 日本人配偶者ビザ-結婚ビザの法務Q&A
- Q: 配偶者ビザとは、どのようなものですか?
- Q: 配偶者ビザの要件(基準)は何でしょうか?
- Q: 実務では、「同居」が重視されているようですが、同居を重視するのはおかしいのではないですか?
- Q: 配偶者ビザは内縁でも取れますか?
- Q: 配偶者ビザが内縁ではとれないということにどうしても納得がいきません。
- Q: 愛人は入国管理局ではどう扱われますか?
- Q: 日系人の配偶者は配偶者ビザをもらえますか?
- Q:私は配偶者ビザを持っていますが、日本の大学に入学してもよいでしょうか?
- Q: 配偶者ビザでは仕事に制限はありますか?
- Q: 配偶者ビザを申請するときはどういうことを入国管理局に聞かれますか?
- Q: 海外で働いている日本人が配偶者同伴で(同時に)、入国(帰国)する場合の配偶者ビザの認定(COE)につき、書式の書き方を教えてください。
- Q: バルト三国は査証免除の国があるのですが、査証免除で来たところ、以前上陸拒否されたことがあったせいか、初回15日、粘りの更新でも+15日で、諸般の事情から婚姻手続きが間に合わず、配偶者ビザの申請ができず、窮境に陥っております。明日が最後の在留期限です。航空券を持ってくれば更新を検討するとも言われてますが、これも諸般の事情から困難です。どうすればよいでしょうか。
- Q: 結婚するかは未定なので配偶者ビザの申請はできませんが、とりあえず、日本に在留させたい彼女(彼)がいる場合、どうすればよいですか。
- Q:配偶者ビザを取るのですが、インド大使館では独身証明書は取得出来ないと、法務局の人に言われました。ビザがないのですか?
- Q:性同一性障害が同性の相手と同居するための配偶者ビザ等の在留資格はあるのでしょうか。国際養子縁組はどうでしょうか。あるいは、相手が日本人との子どもを妊娠した場合はどうでしょうか。
- Q:半年前に在特許可されたばかりの外国人女性が、その夫(日本人)とは離婚をする予定です。彼女と再婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)は更新できるでしょうか。
- Q:日本人配偶者(配偶者ビザ)の身分で帰化した後、離婚した場合、日本国籍はどうなるでしょうか。
- Q:外国国籍の男性とA国で結婚し、現在はA国に居住しています。この点、A国の法律にしたがって入籍しましたが、私はA国国籍ではなく日本人のままです。その私が日本に戻って働く場合、(1)外国人配偶者も呼び寄せることが出来ますか。また、(2)その際に外国人配偶者は日本で働くことは出来ますか。日本滞在は数年の予定で、その後A国に帰るために外国人配偶者は日本国籍を申請するつもりはありません。また(3)日本へ来る際に外国人配偶者も一緒に来れますか。
- Q:短期ビザで日本滞在中、日本人の子どもを妊娠しました。すぐに結婚はできませんので、配偶者ビザを取れません。子どもは日本で産んで一緒に育てたいと思っています。このような場合、出産後、母親と子どもは日本に住むことは可能でしょうか。また、他の国のように婚約者ビザのようなものはあるのでしょうか。
日本人配偶者ビザ-結婚ビザの法務Q&A

一般的な国際結婚を経験するご夫婦は、お相手の国の渉外戸籍の知識はある程度は必要になるので、身につけることになります。ただ、弊所のようなイミグレーションコンサルタントは、そうした限定的な知識ではなく横断的に俯瞰してご案内致します。
Q: 配偶者ビザとは、どのようなものですか?
A: 配偶者ビザとは、「結婚ビザ」、等と称されることもありますが、正確には日本人配偶者等と、永住者の配偶者等の2種類があり、ここでは便宜上、日本人配偶者を念頭に申し上げます。
これは、「日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」のことをいいます。
いわゆる国際結婚で、妻や夫を呼び寄せるときはこのビザであり、「スパウズ・ビザ」として日本のビザの代表の一つともいえます。但し、「技術」や「企業内転勤」等の在留資格を有する外国人が妻や夫を呼ぶような場合は「配偶者ビザ」ではなく、「家族滞在」という在留資格の範疇です。
他方、特別養子縁組というのは、そもそも養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と対比してより縁組の効果(実方との断絶等)が大きく、その分、成立手続きも複雑な特殊な養子縁組のことをいいます。なお、国際養子縁組については、たとえばパキスタン人の子どもでも養子縁組は可能である等、まだまだ流動的な分野が残されています。
そして、「日本人の子として出生した者」には、認知された非嫡出子を含みます。この辺りは、民法の親族法の知識も必要です。
ちなみに、配偶者ビザと類似の概念として「フィアンセビザ」というものもありますが、日本の入国管理局の場合、「フィアンセビザ」という概念はありません。すなわち、「フィアンセビザ」のカテゴリーは、短期滞在の枠内で処理されます。
Q: 配偶者ビザの要件(基準)は何でしょうか?
A: 最も重要なのは、入管法上の「配偶者」概念は、民法上のそれよりも、狭い、ということです。具体的には、単に法律上、婚姻しているのみでは足りず、夫婦としての実体(実態)の伴ったものでなければなりません。これは偽装婚を避ける意味でやむをえないところであります。もし、単に婚姻していればよいのであれば、入管管理局は配偶者ビザで埋め尽くされることでしょう。
また、最近、最高裁判例が出て、配偶者ビザの範囲を実質解釈し、従来よりも狭める判断をしていますから、注意が必要です。判例というものは、高裁レベルまでのものと最高裁とでは全く重みが違います。
なお、離婚すると配偶者ビザを「当然に」喪失するとの「学説」がありますが、異説であり、実務も現場もそのような見解は採用しておりません(公定力)。在留資格該当性と在留資格そのものを混同しているきらいがあります。
Q: 実務では、「同居」が重視されているようですが、同居を重視するのはおかしいのではないですか?
A3: これは、要するに、入管法上、保護に値する夫婦関係の解釈の問題です。確かに、歴史的には日本でも通い婚の形態はあったわけであり、また国際結婚である以上、「同居」を常識かのように押し付けるのは、問題なしとはしえないでしょう。しかし、相変わらず、偽装婚は多いですし、別居が夫婦関係の破綻の強力な推定資料になるのも事実です。そして、住民票や外登、あるいは実態(体)調査等で住所等は外形的に識別できます。それゆえ、同居か別居かを重視するのはやむをえないでしょう。ですから、仕事の関係等で一時別居するとき等は注意が必要です。
Q: 配偶者ビザは内縁でも取れますか?
A: 実務上、取れません。内縁関係が保護されるというのは入管法では特殊例外的場面で、たとえば、実子を保護することの「反射的効力」として、「結果的に」保護されるような場面です。
この点、内縁関係が入管法の保護対象から基本的に除外されているのは、あたかも民法177条の法意に類似するとも言えましょう。すなわち、177条は「公示の原則」を定め、いわゆる表示主義ないし、外形主義の見地から実体関係というよりはむしろ画一的に処理するほうを優先させます。これは、もし、実体関係を審査すると、民事手続きは渋滞するから、というのが一つの理由です。そこで、同じようなことが入管の手続きにも言えるといえましょう。たとえば、外国の中には婚姻の届出のことを「登記」と称する国があるのです。「登記」して婚姻を公示させて法律関係の安定に資する、というわけです。そして、もし入国管理局の手続きで内縁関係を一つ一つ審査し、その中で保護に値するものを分別していたら、今でさえ渋滞しているのに、ますます渋滞して機能しなくなることでしょう。
とはいえ、他国の入管制度では一定の内縁関係で配偶者ビザを付与する例があります。たとえば、当該内縁関係が、その外国人の母国においては、法律婚とあらゆる点で同一の法律上の権利義務関係を有すること等を要件として、これを認容する立法例があります。
Q: 配偶者ビザが内縁ではとれないということにどうしても納得がいきません。
入管法に「配偶者」と書いてあるから、民法上の婚姻が必要、ということですが、その一方で入管法と民法上の配偶者とは別の概念であると解釈され、法概念の相対性論を認容して、同居等の実質的な婚姻関係を重視しています。だとすれば、まさしくその「法概念の相対性理論」によって、入管法上の「配偶者」には内縁を含む、と解釈することは可能であります。のみならず、内縁はまさに「実質的な関係」なのですから、実質関係を重視するならば、法解釈の権衡上、内縁は無視できなくなるはずです。それにそもそも、内縁というのは親族法関係の最高裁判例及び民法学の通説では厚く保護されてるわけですから、おかしくはないですか?
A: この問題は配偶者ビザかどうかということが問題なのではなく、実質的に保護に値する場合に、いかなる在留資格該当性を認容するべきかという問題です。そして、配偶者ビザは定型的・類型的に在留資格該当性を判断するべきだと解するのであれば、配偶者ビザの問題ではなく、非定型的判断に馴染む他の在留資格の問題だということになるでしょう。
日頃は配偶者ビザにつき、このような問題を考えることはほとんどありませんが、法理論的には問題があります。刑法と民法すら関係があるわけで、まして民法と入管法は本来、密接な関係があり、身分関係のビザというのは、そもそも民法解釈を前提にしているのです。民法というのは法律学の中心であり、特に制限の無い限り、全ての法令にその射程距離が及ぶものです。また、入管法の制度趣旨(憲法13条等)から見ても、何の保護も与えなくてよいというわけではありません。
ただ、配偶者ビザでなくとも、特段の事情があれば、定住者等で保護されることはあり得ます。この問題は流動的な側面があるので、今後も問題になるでしょう。というのは、国際結婚の場合、日本人同士とは異なり、前婚の離婚が絡むと渉外離婚案件になって、カトリック国等では(国にもよりますが)容易には離婚できませんし、渉外離婚訴訟も高額になりますから簡単にはできず、その結果、内縁関係が非常に多く生ずるからです。
Q: 愛人は入国管理局ではどう扱われますか?
A: 「日本人の配偶者等」としては、認容されません。つまりは配偶者ビザは困難です。愛人と内縁の区別は民法の本に書いてありますから、研究したほうがよいでしょう。結論として、入管法ではもとより、民法でも「愛人」というのは、基本的に保護されません。同様に重婚的内縁関係も保護範囲が狭くなります。愛人という用語を用いるかは別として、そういう場合、ほかの在留資格を検討するほかありません。
Q: 日系人の配偶者は配偶者ビザをもらえますか?
A: ここでいう「日系人」には日本国籍者を含まないと前提した場合、日系人の配偶者は、一般には、「配偶者ビザ」の問題ではなく、当該日系人が定住者ビザならば、その配偶者も基本的には「定住者ビザ」となります。ただ、日系人の中には「日本人=日本国籍者」も多く見られますから、ご自身の戸籍は調べておくほうがよいでしょう。
Q:私は配偶者ビザを持っていますが、日本の大学に入学してもよいでしょうか?
A: 特に制限はありません。自由に大学へゆけます。
Q: 配偶者ビザでは仕事に制限はありますか?
A: 特にありませんが、風俗関係で就労していた場合、更新時にトラブルになる場合が多いです。就労上の制限が無いのが特徴の一つであり、それゆえに偽装婚が絶えないのです。偽装婚はアメリカでは映画になったこともありますが、実は犯罪です(公正証書原本不実記載罪。)。日本人も外国人も処罰されます。
Q: 配偶者ビザを申請するときはどういうことを入国管理局に聞かれますか?
A: 根掘り葉掘り聞かれます。実際には文書で質問書の形で行うのが原則ですが、たとえば、「初めて出会ったのはいつか。」、「どこの場所か。」、「誰から紹介を受けたか。」、「離婚歴はあるか。」、「結婚に至った経緯は何か。」・・・等々。また、お二人のスナップ写真等もデフォルトで要求書類です。
もちろん、入国管理局の職員も好き好んでそのようなことを聞いているのではありません。偽装婚が多いために配偶者ビザの審査上、やむなく聞いているわけですから、ある程度、理解も必要です。そういう意味で、この場面のプライバシー権(憲法13条)は「公共の福祉」(憲法12条、13条)という内在的制約を受けていることになります。
なお、入管の指示どおりに用意しても不許可になることは当然にあります。
Q: 海外で働いている日本人が配偶者同伴で(同時に)、入国(帰国)する場合の配偶者ビザの認定(COE)につき、書式の書き方を教えてください。
A: 以下は配偶者ビザに係る特定の行政指導を前提にした解釈です。
「本国における居住地」=本国以外に居住しているときは、本国に帰国するときの居所または、本国で最後に居住していた場所、に加え、現在の当該外国の居所を併記。
「日本における連絡先・電話番号」=原則として、日本人側の、在日の親族の連絡先。
「滞在予定期間」=無記入またはPERMANENT(等。幅があり、あまり明確ではありません。筆者はPERMANENTと書いたときに、「PERMANENTではダメです!」との行政指導を得たことがありますが、それは入管協会の書式集に依拠するものであって、職員が知らなかったようです。)
「同伴者の有無」=YES(当該日本人のこと)
「在日家族(新書式では「在日親族及び同居者」)」=親族を記入(兄弟姉妹を含む)
「婚姻等届出年月日」=戸籍謄本に記載されているもの。外国で先に婚姻したときは、証書の日本への送付年月日の記載(・・・という行政指導は存する。)。
「22(新書式では「24」) 扶養者」=日本人側(夫または妻)に扶養能力のあるときは、当該日本人。なお、「勤務先名称」「所在地」「電話番号」「収入(新書式では「年収」)」、につき、日本へ帰国することに伴い、転職する予定があるときは、まず、現職に関してのそれぞれの事項を必ず書く必要があります(必要的記載事項)。そして、日本での転職先については、申請書の当該欄に併記する形でも構いませんし、又は、別添の理由書ないし説明書に記載することになります(任意的記載事項ですが、事実上は必要的。)。ちなみにこれとの関係で言えば、在職証明書は現職のもの、転職先については雇用(予定の)契約書、を提出することになります。
「23(新書式では「25」) 在日身元保証人又は連絡先」=第一次的には、当該日本人側の親族(親等)等がなると解してもよいでしょう。当該日本人自身はなれません(東京入管の特定の行政指導。但し、この種の行政指導は可変的です。)。日本人配偶者自身に十分な収入があるときは、これは形式的なものになりますので、親が年金生活者でもよいです(年金の証明書を提出。金額は重要ではない場合もあります。)。ちなみに、日本に全く身寄りがなく、親族のいない(かまたは協力の得られない)場合、認定は取れず、いわば原則に戻って、在外公館で直接査証申請する形になるとの行政指導が存します。
「24 申請の提出者(代理人)」(新書式では「26 申請人又は代理人」)=23(新書式では「25」)と同様、一般には、第一次的には、当該日本人側の親族(親等)がなります。「署名」は、その当該日本人側の親族等(親等)の自筆になります。その自筆(署名)部分以外は全てワープロでも構いません。
なお、COEの「本邦に居住する本人の親族」が、「代理人」(法施行規則別表第4「日本人配偶者等」)となる、ということの、その「親族」の要件については、この別表4にいうところの「本人」とは当該外国人のことをいうものと、同別表4に定義されておりますので、それが前提となります。そして、結論として、「親族」はどこまでを「親族」と評価されるかについては、たとえば、「本人」たる当該外国人の在日の実兄(外国人。在留資格=たとえば、こちらも日配とします。)は、「親族=代理人」に含まれます。これは、特に特則たる制限規定がない以上、全ての法令の一般法たる、民法上の「親族」の範囲(血族は6親等まで、姻族は3親等まであり、広範です。民725条。)の当然適用に委ねたものと解されます(したがって、当該外国人の当該実兄は代理人たり得る。)。ただ、実務上は、あまり疎遠な親族よりは、審査上、親等が近いほうがよい場合は多いでしょう。
なお、このような同伴帰国では日本人側の住民票は要りません。ただ、筆者は相談者から、配偶者ビザの認定(COE)につき、「住民票が必須かのような話を友人から聞いたのですが・・・。」との相談を受けることもありますが、それは一般的な話の表層を聞いたものと思われます。
Q: バルト三国は査証免除の国があるのですが、査証免除で来たところ、以前上陸拒否されたことがあったせいか、初回15日、粘りの更新でも+15日で、諸般の事情から婚姻手続きが間に合わず、配偶者ビザの申請ができず、窮境に陥っております。明日が最後の在留期限です。航空券を持ってくれば更新を検討するとも言われてますが、これも諸般の事情から困難です。どうすればよいでしょうか。
A: 査証免除と言ってもGNP等からみてギリギリと言えますが、どこか外国人パブで就労するのではないか、等の疑いをかけられたのかもしれません。
さて、一般に国際結婚手続そのものが何らかの事情で困難な場合、まず、配偶者となる相手も同伴して(連れ子がいれば連れ子も同伴してもよい。)、担当となる市区町村の戸籍担当の課の職員のうち、最も詳しい職員と徹底的に打診・交渉し、かつ所管法務局とも打診・照会して裏づけを取ることです。そして、現況で入手可能な限りの文書を揃えて区市町村の戸籍担当の課へ行き、第一次的に「受理証明」、第二次的に「受付証明」の交付を請求します。この即時「受理」と「受付」の差異は実務に触れている方は御存知と思いますが、グレーゾーンがあり担当職員の裁量があるのは否定しがたいところです。特に、あまり多くある国ではないときはその傾向が出ます。
私の経験で、もうダメかというような在留期限切れの当日に受理証明が出され、その日の15時59分に入管で配偶者ビザに係る変更申請が受理されたことがあります。このようなときは手続きに精通した人間でないとできないことがあります。またこのような場合、必ずしも全ての書類を揃えて配偶者ビザ申請を行う必要はないです。受理証明書、住民票、旅券、程度しかなくともよく、課税・納税関係の証明書等のその他は追完扱いでも構いません(受付の整理番号を明記した添え状を添付して郵送による追完で可。)。追完扱いの場合、たとえば14日以内に入管必着にて追完せねばならず、もし事情により間に合わないときはその旨を入管へ連絡せねばなりません。
Q: 結婚するかは未定なので配偶者ビザの申請はできませんが、とりあえず、日本に在留させたい彼女(彼)がいる場合、どうすればよいですか。
A: その方の国籍、経歴、学歴、等の諸般の事情を総合的に考慮して、日本に在留する資格を得られることはあり得ます。WEB上で実務の最前線で通用するあらゆる情報を網羅するのは不可能ですから、かいつまんで、一つのパターンを言えば、就学、留学、就労のレールに載るような場面もあるでしょう。ただ、本人の意思や資質、そして、これまでの日本での在留履歴、日本で何をやっていたのか、が問題になることが多く、短期滞在も困難な場面が実際にあります。また、「虚偽」の申請はできないことにも留意が必要です。
Q:配偶者ビザを取るのですが、インド大使館では独身証明書は取得出来ないと、法務局の人に言われました。ビザがないのですか?
A:この設例は次のように分析しましょう。
まず、「独身証明書」と「婚姻要件具備証明書」を分けて考えましょう。「婚姻要件具備証明書」を発行しない国は多数ありますが、「独身証明書」の類を発行しない国は稀です。
次に、インド母国での発行と、在日大使館での発行とを分けて考えましょう。日本で結婚する場合、証明書類は、母国での発行でも、在日外国公館での発行でも、基本的には差し支えません。
さらに、「配偶者ビザ」と「結婚」を分けて考えましょう。「配偶者ビザ」がなくても「結婚」できますし、「配偶者ビザ」があっても「結婚」できないこともあり、配偶者ビザの有無と結婚とは直接関係ありません。
最後に、外国政府の取扱というのは、非常に流動的です。以前ダメでもいまはOKということは日常茶飯事ですし、逆に以前OKでも今はダメということもあります。常に今はどうなのか、を確認しましょう。
Q:性同一性障害が同性の相手と同居するための配偶者ビザ等の在留資格はあるのでしょうか。国際養子縁組はどうでしょうか。あるいは、相手が日本人との子どもを妊娠した場合はどうでしょうか。
A:この設例もたまに受けるご設例です。性同一性障害の保護は日本ではあまり進んでいません。ましていわんや、入国管理局という人権「制約」的分野で「性同一性障害の保護」など射程に入っていない、というのが入国管理局の実体と思われます。結論として、現段階では当該「愛」を(日本で)、配偶者ビザ等で実現する制度的に用意されたシステムは日本にはありません。
そこで、試行錯誤を繰り返すしかないでしょう。まず、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律を活用できないか検討しましょう。また、同法の適用の有無に関わらず、入国管理局的には、その人が日本で在留特別許可が可能なほどの日本との密接な結び付きを持っている必要があるかもしれません。
その際、日本での有効性は別として、外国で同性婚を認容している国で婚姻を成立させておく等の実績作りも検討するべきかもしれません。たとえば、いきなりその人との同居を理由に呼ぶのは困難です。配偶者ビザ等に係る在留資格該当性がないでしょう。
この点で、発想を変え、相手がまだ若いのであれば、お友だち等が、費用を負担し、日本の日本語学校>専門学校>就職、等といった流れに乗せることも検討してもよいでしょう。彼女が就労の在留資格を持っていれば、あなたと同居してようが、日本の憲法、法令では、基本的には自己決定権の問題です。
なお、養子についてはよく考えましょう。年齢に要件があり、基本的に成人同士の養子では在留資格は許可されません(厳密には、未成年者を養子にしても、不許可な場合が多い。)。ちなみに、最近、成人同士の養子縁組で裁判所が在特相当との趣旨の判断を出しましたが、私などは非常に意外な感を持ったほどの特例中の特例です。養子だけでどうこうするのであれば、入国管理局との裁判が待っている場合が多いでしょう。
また子どもの妊娠とかも考えておられるようです。違法行為は行ってはなりませんが、日本人の実子を養育するために在留資格が許可されることは全く無いとまでは言えません。
Q:半年前に在特許可されたばかりの外国人女性が、その夫(日本人)とは離婚をする予定です。彼女と再婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)は更新できるでしょうか。
A:この設例も時々あります。在特の履歴が無くとも、再婚の事案一般に妥当する話です。
偽装結婚ではないことが前提ですが、これは一般には、急いだほうがよいケースでしょう。なぜなら、在特で初回にもらう配偶者ビザの期限は1年間です。他方、離婚したときの待婚期間は、原則的には、半年です。然るに現在、配偶者ビザの在特許可後、半年経過となれば、もう更新に間に合わない時期です。
この状況でしばしば見られるパターンなのですが、夫婦関係が(後発的にせよ)破綻しているのに、とりあえず、外形を取り繕って、配偶者ビザを更新申請させるパターンです。そのパターンの場合、更新申請の審査中に、入管に呼び出され、偽装婚の嫌疑をかけられて、結局、突如として帰国させられるというパターンが目立ちます。注意事項ですが、夫婦関係が破綻している場合、基本的に配偶者ビザを更新できないと想定しておくべきなのです。
他方、再婚による「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)の許可は、全力で準備すれば許可されることはあるでしょう。全力で準備、とは、入国管理局へ出す資料の中身、入国管理局とのネゴシエイション、入管の制度やシステム、運用や解釈、入管の組織等を理解したうえでの適切な対応、等のことを言います。
私の知っている例で在特(配偶者ビザ)許可後に離婚、更新が不許可になって、いったん国外に追い出されて、紆余曲折の結果、別の日本人と再婚、さらに紆余曲折の結果、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付され、配偶者ビザで日本で再び在留できるようになった例はあります。
ただ、当該事例が、前婚が偽装婚ではなかったのか、また、後婚の当事者がその偽装婚に関与していたのではないか、等も疑われるでしょうから、反証を用意し、そうした嫌疑を晴らす必要もある場合が多いでしょう。たとえば、結婚までする決心は付かないが、とりあえず、在留させておきたいような場合に、偽装婚に加担するような動機が生じないとも言えないでしょう。入管の業界人ですと、そういう目で見るのです。
[参考(日本の役所での「創設的」婚姻届の可否)]
| 日本人側が日本にいる | 日本人側が相手の国にいる | 日本人側が第三国にい | |
| 外国人側が日本にいる | ○ | ○ | ○ |
| 外国人側が自分の国にいる | ○ | ○ | ○ |
| 外国人側が第三国にいる | ○ | ○ | ○ |
Q:日本人配偶者(配偶者ビザ)の身分で帰化した後、離婚した場合、日本国籍はどうなるでしょうか。
A:「帰化」とは、この文脈では、日本の国籍の付与を許可されたという意味です。この設例のように、帰化した後、離婚した場合、日本国籍はどうなるか、という設例は非常に多いです。ところが、市販の本には書いていません。それもそのはず、机上の理論だけで書いているからです。現実的な設例に答えるこのサイトは非常に貴重です。
さて、このような設例は、日本人と結婚し、永住申請をして許可された後、離婚した場合どうなるか、という設例と基本的にパラレルに考えられます。通常であれば、日本国籍を失うことはありません。そのため、入国管理局も法務局も偽装婚や片面的偽装婚のチェックが必要です。ところが、民間の目で見て、無意味に厳しい場合と濫りに手抜きの場合が交錯し、審査のレベルが均一ではありません。
Q:外国国籍の男性とA国で結婚し、現在はA国に居住しています。この点、A国の法律にしたがって入籍しましたが、私はA国国籍ではなく日本人のままです。その私が日本に戻って働く場合、(1)外国人配偶者も呼び寄せることが出来ますか。また、(2)その際に外国人配偶者は日本で働くことは出来ますか。日本滞在は数年の予定で、その後A国に帰るために外国人配偶者は日本国籍を申請するつもりはありません。また(3)日本へ来る際に外国人配偶者も一緒に来れますか。
A:一緒に来て、かつ、すぐに就労できるようにするためには、一般には、事前に「日本人の配偶者等」の在留資格に係る在留資格認定証明書を申請し、かつ、交付され、かつ、配偶者ビザの査証申請をし、かつ、発給され、かつ、上陸申請をして、かつ、上陸許可を得ることです。在留資格認定証明書の審査には数か月かかる場合もあり、早めの準備が重要です。
他方、短期滞在で上陸した場合、そこから「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)に直接変更できるかは流動的で当てにならないため、一般の人が行うときは、在留資格認定証明書の申請を経由することになります。なお、プロがやる場合には、認定と変更申請と短期の更新を重畳させて、帰らずに済ませる例もありますし、最近の当事務所の事例では、ほとんどは認定経由なしの直接変更を採っています。なんらかの理由で、認定を経由させる場合、ゆっくりやっていると、短期滞在の期限内に認定が交付されず、かつ、短期の更新申請も断念するよう行政指導されて、帰国することになることも多いでしょう。
日本人の配偶者等の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を得たときは、就労は可能です。
Q:短期ビザで日本滞在中、日本人の子どもを妊娠しました。すぐに結婚はできませんので、配偶者ビザを取れません。子どもは日本で産んで一緒に育てたいと思っています。このような場合、出産後、母親と子どもは日本に住むことは可能でしょうか。また、他の国のように婚約者ビザのようなものはあるのでしょうか。
A:短期滞在で在留中に妊娠が判明した時点で、もう在留期限はほとんど無いでしょう。他方、妊娠中の女性を日本に在留させるための配偶者ビザ等の在留資格は特にありません。たとえば、婚約者ビザのようなものは、正確には、ありません。したがって、このような場合、原則、いったん帰国しなければなりません。
もちろん、プロの行政書士の場合、例外的手法を執ることが可能な場合はありますが、ここには書けません。行政書士は、入管では、あたかも新聞記者のような活動をする場合もあり、新聞記者のマナーともいえる取材源の秘匿が問題になるうえ、機密性の高い情報を扱わざるを得ず、そのことが、クライアントに質の高い情報や特別の配慮を、「継続的に」提供するうえで、重要であるためです。たとえば、入管と、「その場しのぎ」で一時的に付き合うだけならば、別に何の遠慮も要らないかもしれません。しかし、「ここだけの話にしておいて欲しい。」等という前提で得た情報や特別の配慮を全部公開してしまうのでは、「あの人は信用できない。」という話になり、その後、情報や特別の配慮を得られなくなってしまう場合があるのです。そうなった場合、結局、「本当に困っている方」を助けることもできなくなり、意味がありません。また、そうなれば私自身、仕事が成り立たなくなり、その結果、こういうサイトを無料で公開することもできなくなり、サイトを閉鎖することになるわけです。
これは、入管専門行政書士の仕事の性質上、やむを得ないことと思われます。ご諒承下さい。なお、公開できる部分は、筆者の他のサイトで公開致します。
他方、妊娠が進行し航空会社が載せなくなるような状態であれば、人道的理由で短期滞在等の申請を検討することもあり得るでしょうが、これは配偶者ビザとは異なります。
さらに、適法に在留しているときに、子どもが生まれた場合、一般には胎児認知していれば、日本国籍ですから子どもは日本に居られます。その母親たる外国人については、親権、現実の扶養、生計の安定等の基本的原則のもとで、実子養育のための在留資格(定住者)の申請を行い、許可される場合はあり得ます。
他方、適法に在留していないとき(不法滞在)に、子どもが生まれた場合、一般には胎児認知していれば、日本国籍ですから子どもは日本に居られますが、その母親たる外国人については、入国管理局に不法滞在等の違反事実を出頭申告し、親権、現実の扶養、生計の安定等の基本的原則のもとで、実子養育のための在留資格(定住者)の在留特別許可をされる場合は無いとは言えません。「定住者」の在留資格は、その法的効力において、配偶者ビザと大差ありません。
なお、このような未婚の母親の類型の場合、入国管理局の考慮する保護法益は、子どもの保護であって、基本的には、内縁の保護を考慮しているものではありません。なお、参考までに申し上げれば、このような人道的配慮を奇貨として、本当は外国人同士の子どもにも関わらず、金員に困窮した日本人に金員を渡し、「偽装認知」させ、「虚偽の日本人の子ども」を作出させ、日本在留を企図する事案がしばしば摘発され、逮捕されています(偽装認知は、公正証書原本不実記載罪で明らかな犯罪です。)。そのため、この種の事案も入国管理局としては、最初から信用することはありません。「本当にあなたの子どもか?どういうきっかけで知り合ったのか?」等という視点で審査されます。